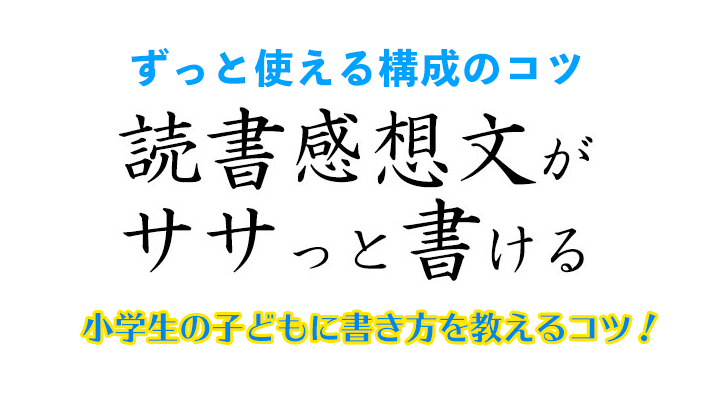
学習を楽しむ
【春休みの課題もクリア!】読書感想文の書き方を小学生の子どもに教えるコツ!
夏休みの宿題や入学・進級前の課題などをはじめ、小学校・中学校・高校を通して課題として出され続ける読書感想文。読書感想文を苦手と感じているお子さんは比較的多く、高校生にもなると課題の本や論点なども難しくなり手が付けられず……なんてことも。
逆に学生生活で何度も書く機会のある課題なので、ハードルの低い小学校時代だけでも書き方のコツを指導してあげれば、学年が上がるごとにステップを踏んでどんどん書けるようになるのではないでしょうか。
今回は、小学生の読書感想文の書き方を紹介します。書き方のコツをつかんで、小学生のお子さんの感性や表現力を引き出し、「読書感想文なんて簡単!」という意識づけを目指しましょう。基本的な読書感想文の書き方を応用できるようになれば、いつ読書感想文の課題が出てもすらすらと書けるように!ぜひ書き方の参考にしてみてください。
●毎月の作文ワークで書き方が学べる!名探偵コナンゼミの国語教材を今すぐおためし!
小学生の読書感想文、書き方のプロセス確認!

はじめに、小学生の読書感想文の書き方のプロセスを確認しましょう。
- 本を選ぶ
- 本を読む
- 読書感想文全体の構成を立てる
- 構成をより具体的にして下書きする
- 清書する
これが、読者感想文を書くためのシンプルな手順です。
小学5、6年生の高学年になると国語で読書感想文の授業があるので、この手順を踏みながら自分で組み立てていけるようになりますが、低学年・中学年のうちは、必要に応じておうちの方がサポートしつつ、読書感想文の書き方の工程を確認しながら組み立てていくことが大切です。
まず、本選びには鉄則があり、読み方にもちょっとしたコツあります。また、読書感想文の構成は型に当てはめれば簡単に決まります。下書きをする過程では大筋を具体的にするときの着眼点を持ち、コツをつかむことが必要ですが、ここまできたら完成まであと少し!原稿用紙の使い方を確認しながら、丁寧に清書すれば完成です。
それでは、早速、小学生向け!読書感想文の書き方のプロセスをひとつひとつチェックしていきましょう。
1.読書感想文の本を選ぶ/書き方の質に影響する「子どもの興味」
読書感想文書き方は本選びから始まっています。
読書感想文の本選びのコツは、子ども自身に選ばせること。
大人が選ぶとつい、子どもに読ませたい内容かどうか、感想文を書きやすいかどうかということを気にしてしまいます。
また、大人が選んだ本が必ずしも子どもが読みたい本だとは限りません。
読書感想文といえば、「青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書や伝記などから選んだほうがいいのでは......と思うおうちの方もいるかもしれませんが、最も大切なのは、子どもが興味を持っている本かどうか、楽しく読めるかどうか。また、自分の体験にどこまで落とし込めるかといった子どもの世界が重要にもなってきます。
子どもの視点でどこまで読書体験から気づきを得ることができるか、子どもがどこまで読書感想文に対してモチベーションを高められるか、実はこれが読書感想文の書き方最大のコツともいえるかもしれません。
どんな本がいいのか、どうしていいのか、あの本の方がいいかもしれない、など、お子さんと一緒に楽しく話しながら本選びをしてみましょう。
また、本にはたくさんのジャンルがあります。小説などフィクションの物語の他にも、伝記や随筆、社会問題に関する啓発本など、見渡せばたくさんの種類の本があります。お子さんの興味のアンテナを大切に本選びをしましょう。
2.本を読む/付箋を活用するのがおすすめ!

本を決めたら早速本を読み始めましょう。読書感想文の書き方のコツ2つ目は、その読み方です。
おすすめなのは、付箋を使うこと。
読み進めていく中で、心に残った場面やセリフ、どうしてそう思ったのか、必ず胸を打たれる瞬間が出てくると思いますが、読んで終わった後にすべてを覚えているというのは難しいですよね。
驚いたり、おもしろいと思ったり、すごいと思ったり、悲しいと思ったり、うれしいと思ったり......なんらかの感情が湧き起こったページに付箋を貼っていきましょう。
また、このとき、どのような気持ちになったのかを一言メモとして付箋に書いておくようにします。余裕があれば、なぜそのような気持ちになったのかも書いておきましょう。
ページをめくるのを面倒くさそうにしているお子さんであれば、「この主人公はどんな子?」と聞いてみたり、書いた付箋の内容にリアクションしてあげるのもモチベーションアップに良いかもしれません。コミュニケーションを意識しながら読み進めてみてください。
また、「あとがき」を読むのもおすすめです。あとがきにはこの本がどういう風に書かれたのかという作者や作品関係者の思いなどがつづられていることが多く、読書体験をより鮮やかなものにしてくることもあります。
読書体験を通して自分が伝えたいことの参考にもなるでしょう。
3.構成を立てる/読書感想文の書き方のコツは「3つの柱」で!
続いて、いよいよ、本格的な書き方へ。小学生の読書感想文の構成の組み立て方についてみていきましょう。読者感想文は、実は、たった3つの柱で書けます。読書感想文のテンプレートとしてこの流れを覚えてしまいましょう!
<読書感想文3つの柱>
- はじめ=読むまえのこと/本を選んだ理由など
- 真ん中=読書体験/あらすじ+思ったこと
- 終わり=読んだあとのこと/自分の体験なども交えながら
具体的にこれらの書き方について解説していきましょう。
1.はじめ=読むまえのこと/本を選んだ理由など
読書感想文の書き出しである「はじめ」には、読書感想文を書くためにこの本を選んだきっかけを理由もあわせて書いていきます。
書き方の文例)
「姉が読んで感動したと言っていたので、私も読みたいと思いました」
「ぼくの祖父母の家では犬を飼っています。犬種はゴールデンレトリバーで、本の主人公と同じだったことが、この本を選んだきっかけです」
「とてもきれいな花の絵の表紙を目にして、どんな話なのか気になって読んでみたいと思いました。」
例文のように、読んだきっかけは人によってそれぞれ。さまざまなストーリーがあるので、これを書くことでぐっとオリジナリティあふれる読書感想文に近づきます。
2.真ん中=読書体験/あらすじ+思ったこと
「真ん中」は、読者感想文の中でも、最も分量が多くなる部分です。
まず、本のあらすじを簡単に書きます。次に、心に残った場面と思ったことを書いていきます。
あらすじの書き方/文例)
「この本は、小学5年生の女の子3人組が、ケンカを乗りこえて、おたがいの大切さを改めて知る友情ストーリーです」
このように、あらすじは短く簡潔にまとめます。
心に残った場面や思ったことを書くときに役立つが、本を読みながら貼った付箋です。付箋の部分だけを再度読み返し、特に心が動いた付箋に印をつけます。印をつけた付箋の中から「真ん中」に書くことを選ぶとスムーズです。
思ったことの書き方/文例)
- 困難にもへこたれない少年たちを見習いたいと思いました。〜
- 本の中の犬たちが、まるですぐそばにいるように感じました。〜
- 知らない土地に取り残されると、夜も眠れないくらい怖いと思います。〜
そう思った理由や、自分の暮らしの中で実際に起ったことなどを絡めながら肉付けしくと読み応えのある感想になります。
3.終わり=読んだあとのこと/自分の体験なども交えながら
「終わり」は、読んだ後に実際に起こった出来事や、読んだ後に自分の気持ちがどう変わったかを書いていきます。
読んだあとのことの書き方/文例)
「この本を読んで、友達のそうたくんに会いたくなりました。本当はいつも仲良くしてくれてありがとうって言いたかったけれど、はずかしくて言えませんでした」
このように、行動と気持ちがセットになった文章だと、伝わりやすさもアップします。より読んでいて楽しい読書感想文になりますね。
●毎月の作文ワークで書き方が学べる!名探偵コナンゼミの国語教材を今すぐおためし!
4.構成を具体的にして下書き/読書感想文の書き方のコツは「質問で深堀り」!
全体の構成が決まったら、原稿用紙に下書きしていきましょう。前の章で紹介した「3つの柱」の書き方に沿って、文章を書いていきます。
「はじめ」を書くときには「どうしてこの本を選んだのかな?」と質問してあげると、書きやすいでしょう。
「真ん中」を書くときには、まずお子さんにあらすじを説明してもらうといいでしょう。あらすじの説明が長いようであれば、「簡単に言うとどういうことかな?」など声かけしながら、本人にもわかりやすいよう、簡潔にまとめられるようにサポートします。
心に残った場面と思ったことは、まず、付箋を時系列に並べていきます。「前半のページで一番印象に残ったのはどの場面?」「それはなんで?」などと言葉をかけながら、付箋に書かれた「びっくりした」「すごいと思った」などといった感想を具体的にしていきます。
すべてを同じくらい深堀するのではなく、付箋の中でも、最も「大きく心が動いた」感想を深堀りしていくのがポイントです。そうすることでメリハリのある読書感想文になります。
また、学年によって文字数に制限があることが多いです。下書きの段階で意識しておきましょう。
5.清書/原稿用紙の使い方に注意!

下書きが書き終わったら、いよいよ読書感想文の清書。読んでもらうための清書です。基本的なことですが、文字は正しくきれいに書くように心がけましょう。
それから大切なのが、作文用紙の書き方の決まり。注意しながら書きましょう。
<作文用紙使い方のポイント>
・一番右側にタイトルを書く。このとき、上から3マスあけてから書くようにする
・タイトルすぐ左には名前を。姓と名の間は1マスあけ、さらに名の後も1マスあける
・本文は段落のはじめを1マスあけ、話が変わるときは改行し、1マスあける
など、読みやすい読書感想文を目指して確認しながら書いていきましょう。
毎月のトレーニングで読書感想文の書き方が身につく通信教育は?
読書感想文の書き方、もとい、作文を書く力を身につけることができる小学生向け通信教育が小学館の通信教育「名探偵コナンゼミ」。
毎号、語彙力を増やす問題や豊富な読解問題、作文指導などが充実しています。
<名探偵コナンゼミが作文力を身につけるのに適しているワケ>
・基本問題で漢字、語彙、ことばの使い方をしっかりと学ぶ!→自然と語彙力を増やせる。
・読解力を高める問題が豊富!→文章を読み解くコツをつかみ、登場人物の気持ちを理解したり、作者の主張を把握したりする力が身に付く!→読解力や構成力を磨かれる。
・毎月作文に関するワークを掲載!→充実した作文教材で、実践的に学べ、どんどん書き方が学べる。
ぜひ公式HPをぜひチェックしてみてくださいね。
●毎月の作文ワークで書き方が学べる!名探偵コナンゼミの国語教材を今すぐおためし!

©青山剛昌/小学館 ©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996 ©名探偵コナンゼミLLP


 【2024版】小学生の春休みの過ごし方/新学期を見据えたスケジュールの立て方
【2024版】小学生の春休みの過ごし方/新学期を見据えたスケジュールの立て方  一生ものの読解力を身につけたい!小学生の読解力を伸ばすために効果的なこと
一生ものの読解力を身につけたい!小学生の読解力を伸ばすために効果的なこと  時計の教え方〜子どもが楽しく覚える効果的な方法は?〜
時計の教え方〜子どもが楽しく覚える効果的な方法は?〜  1か月受講もOK!冬休みの家庭学習にぴったりな「名探偵コナンゼミ 通信教育」12月号【特別号】!
1か月受講もOK!冬休みの家庭学習にぴったりな「名探偵コナンゼミ 通信教育」12月号【特別号】!  【小学館の探究楽習®オンライン講座参加者大募集】「人体の秘密に迫ろう!」3D空間で人体につい
【小学館の探究楽習®オンライン講座参加者大募集】「人体の秘密に迫ろう!」3D空間で人体につい