
作文の書き方
作文の神様が教える書き方マジック!【3つの鉄則】でどんどん書ける!
作文のワークが毎月充実!小学生向け通信教育なら「名探偵コナンゼミ」
“作文”と聞いただけで、気が重くなってしまう子どもは少なくないはず。
「何から書き始めたらよいか分からない」「書くことが全く思いつかない」「思ったことをとりあえず書くと、ちぐはぐな内容になってしまう」「上手い書き方が分からない」
など、作文が苦手な理由はさまざまですが、小学校・中学校・高校はもちろん、大学受験や卒業論文~就職活動、そして大人になってもなにかと付きまとう作文のスキル。実はちょっとした書き方のルールにを身につければ怖くないのです!
とはいえ作文の書き方をマスターするのはめんどくさそうと思っていませんか?特に小学生に教えるのは大変……。
そこでこの記事では、「作文の神様」として多くの著書を手がける岩下修先生の、作文の書き方の鉄則・テクニックを、実際に作文を書いていく要領で簡単にご紹介します。
目次
- 鉄則1 テーマを決める!タイトルは後回し!
- 鉄則2 作文の構成は「4段落」で書く!
- 鉄則3 書いた後に改めて思ったことをタイトルに!
- 「4段落」構成の作文の書き方は頭のトレーニングにも!
- 小学1年生から作文の書き方が身につく小学生向け通信教育!
鉄則1 テーマを決めて、タイトルは後回し
作文の書き方の鉄則まず1つめは、テーマを決めるのは初めに行うが、最初にタイトルを決めない、ということです。
まずは何に関する作文を書くのか、テーマを決めましょう。例えば今回は【宝物について】書くことにしてみましょう。でも、最初にタイトルを考案するのはNGです。文章を書く前からタイトルだけ書こうとしても悩んでしまうので非効率です。(岩下氏)
テーマを決めたらタイトルもつけたくなってしまいますが、例えば「どんなタイトルにしようかな」と悩んだり、「宝物について書くんだから【宝物について】でいいか」なんて凡庸になったりしてしまいます。いったんここでは我慢!
次は構成に進みましょう。
鉄則2 作文の書き方の重要ポイント!構成は「4段落」で書く!

続いての作文の書き方の鉄則は、構成について。作文の構成の基本は4段落。
作文を序論・本論・結論という3段落で書こうとしたり、起こった出来事を時系列ですべて書こうとする人も多いですが、実は作文は4段落で書くのが鉄則なのです。(岩下)
岩下氏が推奨する作文の基本構造は以下のとおり。例文とともにご紹介します。
1段落(はじめ)…これから自分が書く内容を簡単に紹介する。
導入にあたる部分です。簡単にテーマを説明します。
例:ぼくのいちばんのたからものはつくえです。
2段落(中-なか-1)…テーマに関して何か一つのことを書く。
テーマを掘り下げるための具体的な描写です。例では、テーマである宝物の机の見た目や役目など、客観的事実ともいえる比較的叙事的なことを書いています。
例:しかくがおおくて、ぼくのせのたかさぐらいです。つくえには、ほんがいっぱいおけます。ひきだしが5つあって、ひとつめはトランプやペンが入っています。ふたつめは、わすれてしまいました。三つめは、えんぴつがはいっています。四つめは、おりがみがあります。五つめは、もらったものがはいっています。
3段落(中-なか-2)…テーマに関して何かもう一つ書く。
2段落めとは異なる切り口で、テーマについて書きます。例では、机を誰に買ってもらったのか、どう使っているのか、机にまつわる、自分だけが知っている点を書いています。
例:このつくえは、おじいちゃんがしんじゃう二しゅうかんまえにかってもらいました。おじいちゃんからのさいごのプレゼントです。いまは、そこでべんきょうをしています。つくえは、ぼくのへやのすみっこにおいてあります。
4段落(まとめ)…2段落・3段落を書く中で考えたことをまとめる。
最後に、2・3段落目を踏まえて、考えたことを書いてまとめとします。
例:おじいちゃんがいるとおもってべんきょうしていると、すぐにべんきょうがおわります。
いかがでしょうか。きれいにまとまりましたね。
鉄則3 書いた後に改めて思ったことをタイトルに!
本文ができたところで、最後の作文の書き方の鉄則はタイトルのつけ方です。
最後のまとめは“そのとき自分がどう思ったか”ではなく、“作文を書き終わったときに、改めてどんなことを思ったか”を書けば良いのです。この作文は実際に私の生徒が書いた作文ですが、最後に彼はこの作品にこんなタイトルをつけました。(岩下氏)
【すぐにべんきょうがおわるつくえ】
このタイトルを最初に見たとき、多くの人がこの作文に興味を持ち、内容を読んで納得するのではないでしょうか。
しかし、最初からこのタイトルで作文を書こうとはなかなか思いつきませんよね。
4段落構成で作文を書き、最後のまとめで自分の気持ちを上手に整理することができたからこそ、原稿用紙に自信をもって書けた作文のタイトルなのではないでしょうか。
「4段落」構成の作文の書き方は頭のトレーニングにも!
テーマ作文や読書感想文、論文、入試、就職試験などあらゆる作文のスタイルにあてはめることのできるこの4段落での作文の書き方。
岩下氏によれば、この4段落構成の作文の書き方は、作文をうまく書けるということだけでなく、別のメリットもあるそう。
この方法はすごく頭のトレーニングになります。一つのテーマについて二つのことを設定する、それを類比しながら、うまく差別化しながら書く。これが大変頭を使うのです。(岩下氏)
また、この4段落の作文の書き方は子どもだけでなく大人でも活用できるのだという。
大人がビジネス文書や手紙などで長い文章を書くシーンでも、ぜひこの4段落マジックを活用してみてください。書きたいことが多ければ【なか】を二つではなく三つにすればよいだけなので、どんな長さの文章にも応用することができます。新聞の投書欄を見ていて、うまいと感じる作文はだいたい4段落になっていますね。(岩下氏)
子どもから大人まで使えるこの作文マジック。作文が苦手と感じている方はぜひこの書き方を活用してみてください。
【 岩下修 】立命館小学校国語教育アドバイザー、名進研小学校国語科顧問。だれでも書けるようになり一生使える作文の書き方を全国の子ども達や教師に発進中。“作文の神様”ともよばれている。著書『作文の神様が教えるスラスラ書ける作文マジック』(小学館)ほか多数。
小学1年生から作文の書き方が身につく小学生向け通信教育!
中学受験、高校受験や大学受験、論文、就職の際の試験など、作文スキルが求められる機会はどんどん増えていきます。また、昨今、小学校でも作文の課題は増えており、作文の書き方を身につけるのは早ければ早いほどいいと言えます。とはいえ家庭での指導が難しいのも悩みどころ。
そんなときにおすすめなのが作文ワークが充実している通信教育!小学生向けの名探偵コナンゼミ 通信教育では、小1〜小6まで段階に合わせた作文ワークを毎月ご用意。マンガのセリフを考えるような楽しいワークから、自分の想像したストーリーを表現するワークなど、毎月気軽に作文の書き方のトレーニングができます。また、語彙力問題も充実しているので、表現力を高め文章力をさらにレベルアップできます。
ぜひチェックしてみてくださいね!↓↓

 春休みにおすすめ♪「テーマ作文」を攻略して、書くスキルアップ!
春休みにおすすめ♪「テーマ作文」を攻略して、書くスキルアップ!  書けない子でも楽しく書けちゃう??「うそ作文」のススメ
書けない子でも楽しく書けちゃう??「うそ作文」のススメ 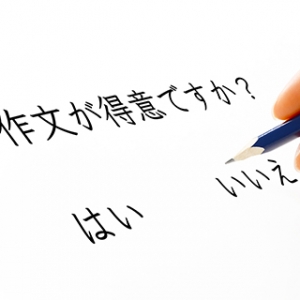 あなたの文章に足りてないのは○○力!作文に必要な5つの力とは?
あなたの文章に足りてないのは○○力!作文に必要な5つの力とは? 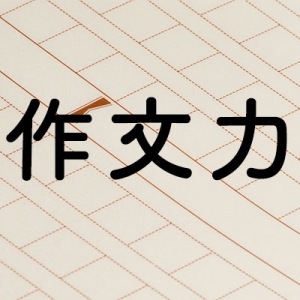 作文の書き方を身に付けるなら「8歳まで」ってホント?!
作文の書き方を身に付けるなら「8歳まで」ってホント?!  【作文の書き方】作文に対する苦手意識を払拭するちょっとしたコツ
【作文の書き方】作文に対する苦手意識を払拭するちょっとしたコツ